蛍火
風が、女の頬をなぶった。
山から降りてくるその風は、目の前に広がる風景とは裏腹に、青き木々の香りを伝えている。
もののふどもの声はすでに遠く、すでに戦場働きの盗人らも仕事を終えたのだろう、下帯ひとつの男達が、死屍を累々と晒していた。
「あんたぁ」
悲痛な女の叫び声が、小川のせせらぎをかき消した。それは山々にこだまを返され、茜色の空に吸い込まれていく。
女は初めよろけるように、そしてしまいには裾の乱れるのもかまわずに、死人の間に駆け入った。
「どきな。あっちへいけ」
があ、と恨めしげな声を上げて、屍骸をついばんでいた烏が飛び去る。それには見向きもせずに女は泥の中に膝をつき、死体の顔を覗き込む。
違う……
こけつまろびつ、女は次の死体に向かう。その度に女の周りを烏が飛び惑う。違う、違う、違う。まるで女は烏と呼び交わすかのようにそう叫びながら、いつの間にか草履を失った素足を青薄で傷だらけにしながら、死体から死体へと飛び回る。
(この戦で手柄をたてりゃあ、親父様も文句はあるまい。帰ったら祝言じゃ)
あんたぁ。
烏が、嘆く。
茜の空は山際にその色をわずかにとどめ、ポツリ、ポツリと星の光が降りはじめた。
烏どもも飽食したのか、遠く山の懐に帰っていった。女は一人、冷えた体を抱きもせず、泥の中に座り込んでいた。
「あんたは嘘つきじゃ」
(これをくれるんか)
(返せよ。母様の形見じゃ)
おう、と笑って背を向けたあの笑顔は、もうどこにもない。
「喉が渇いた」
せせらぎの音が女を誘う。女はいざるように小川へと向かった。しかし萎えた足は草にとられ、川岸を転げ落ちてしまう。
「ここにも……おったか」
ようやく体を起こし、ついた手に、もうなじんだ命を持たぬものが触れる。
女は何の期待も持たぬまま、その顔を覗き込んだ――
あ……
闇の中、目を凝らす。泥に汚れた手を伸ばして、その輪郭をなぞる。
「あんたぁ」
女は、ようやく捜していたものに出会えた。しかしそれは、女に喜びをもたらすはずもなく。
ただ、鎧をはがれた男の体を無意味になでるだけ。何度も顔をうずめた厚い胸。深くえぐられた腹。肩。腕。そして、硬く握り締めたままのこぶし。
そのこぶしが、女の手が触れたとたんに緩んだ。男が握っていたもの――
「これ……」
それは、強く握り締めたためか幾本もの歯を欠いた、櫛だった。御守り代わりにと、女が持たせた柘植の櫛。それを最後に握り締めた男は、何を思っていたのだろう。
「すまなんだ」
渇ききったはずの女の体から、涙があふれた。
「あんたを、嘘つきじゃ言うてしもうた」
まだ櫛をのせたままの男の手を、腕を、掻き抱く。櫛にしずくが、ポトリ、ポトリと落ちる。
そのとき、涙の水玉に、青い光が暗く映った。それは、淡く、そしてもっと淡く、脈動を繰り返す。
(ほんまはの、戦は好かん。こうやって蛍を見ながらお前と酒を酌み交わせさえすりゃ、それが一番じゃ)
それはほんの数日前のことだったのに。
「ああ……」
女は、瞬きもせぬまま、泣き続けた。涙に歪む夜空に、一つ、二つと蛍が舞う。
女はただ、泣き続けた。何時しか、幾百の蛍が、あたりを飛び交うようになっても。
蛍火の華燭が、二人を冷たく照らしていた。
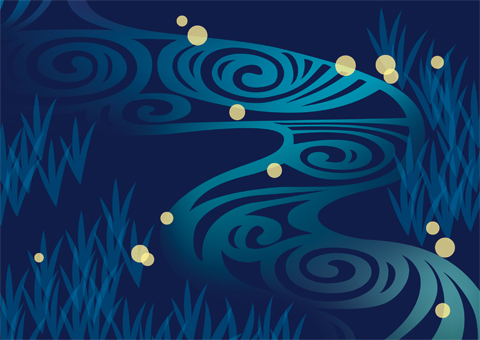
(fin)
