無精卵
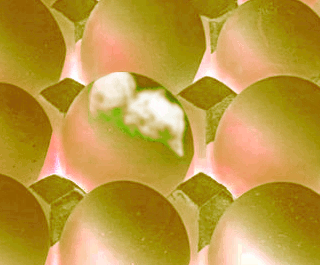
フンフンと鼻歌なんかを歌いながら朝食の用意をしていた私は、ぼさぼさの頭をかき回しながらだらしないパジャマ姿でダイニングに入ってきた洋輔に声をかけた。ああ、とか、うう、とかうなりながらテーブルに着いた彼は、絞ってあったテレビのボリュームを上げる。ちょうど天気予報をやっていた。今日もいい天気。
「あと目玉焼きを作るから」
コンロにはもうお味噌汁が出来てるし、テーブルにはシシャモをもう焼いて出してある。そしてしょうゆとマヨネーズとケチャップ。目玉焼きにマヨネーズをかけるなんて。結婚してもう半年になるけど、いまだに理解できない。やっぱり目玉焼きにはケチャップよね。
熱したフライパンに油を引いて、卵をコンロの角にこつんとぶつけ、フライパンの上に中身を落とす――
「きゃああ」
思わず私は悲鳴を上げた。洋輔が、どうしたと言いながらすぐに駆け寄ってきてくれる。だけど私は口を押さえて、フライパンを指差すことしか出来なかった。
煙を上げるフライパンの上には、ぬれた黄色い羽に赤い血をまとわりつかせた、ひよこがいた。バチバチと油を跳ね飛ばしながらもがいていたそのひよこは、すぐに力尽きたのか動きを止めた。じりじりと焼ける音を立てながら、ひよこの白く濁った眼が私を恨めしそうに睨みつけている。力なく開いた小さなくちばしから、赤い血がジッ、ジッと音を立ててフライパンに落ちる。凍りついたように動けない私の代わりに、洋輔がコンロの火を消して、フライパンの中身を生ごみ入れに捨ててくれた。
「いやー、珍しいこともあるよなぁ。有精卵だったのかな。昔聞いたことがあるよ。卵を割ったらひよこが出てくることがたまーにあるって。今日会社で自慢できるぜ」
そんな明るい彼の言葉に、ようやく私も胸をなでおろした。それでも震える声で、何とか彼に返す。
「ほんと、びっくりした。スーパーのセールで買った卵でも、有精卵ってあるのね」
「ああ、そうだな」
一瞬怪訝そうな顔をした洋輔は、それでもすぐに笑った。
「もう、食おうぜ。目玉焼きは今日はいいや。ご飯をよそってくれよ」
「うん、わかった」
気を取り直して、炊飯器からご飯をよそい、味噌汁を椀に注ぐ。それを手渡すと、ありがとうと、洋輔は笑って言ってくれる。ほんと、あなたと結婚してよかったよ。いきなりご飯に味噌汁をぶっ掛けたりしなかったら、もっとよかったんだけど。
私のご飯はちょっと少なめで。さすがにあんまり食欲がない。味噌汁にひとくち口をつけ、うん、今日はうまく出来た、なんて自画自賛しながらシシャモを頭からかじる。
あれ、なんだろう。歯触りというか、舌触りがなんかおかしい。
口の中が、何かもぞもぞする。口を止めたまま、三分の一ほどかじったシシャモを眺める。
シシャモの腹、卵が詰まっているはずのところから、何か小さなものが皿の上にこぼれだしている。ぴちぴちと跳ねながら。蛆がわいていた。まず、そう思った。
「うぐっ」
私はあわてて口の中身を吐き出した。それらもやっぱり、皿の上でぴちぴちと跳ねる。
「明日美? どうした」
洋輔の声。私は首を振った。それが精一杯だった。口の中のものを全部吐き出してもおさまらない吐き気を必死でこらえる。
「なんだこりゃ……」
洋輔も眉をしかめて、皿の上に吐き出されたものを見つめた。それは、蛆ではなかった。とても小さな、無数の魚。
「シシャモの……稚魚か? なんで。ちゃんと焼いたんだろう?」
私はやっとのことでうなずいた。洋輔は、自分の皿からシシャモを一匹つまみ上げると、それをふたつに割る。だけどそれは、いつものクリーム色の卵が、ぎっしりと詰まっているだけだった。
「おかしいな。こんな話聞いたことがない」
洋輔は、皿の上でうごめいている稚魚の群れを、箸でつつきまわしている。
「ねえ、やめて。早くそれ、捨ててよ」
「あ、ああ。ごめん」
顔の血の気が引いているのが、自分でもわかった。洋輔もそれに気づいてくれたのか、素直に皿を片付けてくれる。もう、なんなんだろう。なんでこんな、おかしなことが。
テレビから聞こえる芸能記者の能天気な声がうっとうしくなって、リモコンを取ろうと腰を上げる。そのとたん、下腹がきりりと痛んだ。
「どうした。腹が痛いのか?」
シンクから戻ってきた洋輔が、心配そうな顔をして私を覗き込んだ。
「ううん。違うの」
私は憂鬱になりながら首を振る。
「あれが……始まったんだと思う。ねえ、片付け、頼んでもいい?」
そういって、まだほとんど手をつけていない朝食を目顔で示す。ああ、と、まだ心配そうな顔でうなずく洋輔を残して、私はダイニングを出た。寝室のタンスからナプキンと生理用ショーツを取り出すと、トイレに入ってはきかえる。だけど、すぐに戻る気がしなくて、そのまま便座に座り込んだ。
なんだったんだろう。最初は卵からひよこが。次はシシャモの卵から、稚魚が。
きりきりと痛み続ける下腹を押さえながら、私はさっきの出来事を反芻していた。
昔は卵から成長途中の雛がまれに出てくることがあったっていう話は、私だって聞いたことがある。だけど、スーパーの安売りの卵が有精卵であるはずがない。鶏舎で雌鳥ばかりが集められて、ただ卵を産まされているだけなんだから。それは、洋輔だってきっと気づいていたはずだ。
それにシシャモだって。……そうよ。洋輔は焼いてあるのかってそんなことを気にしていたけれど、魚は体外受精する生き物だもの。あの卵だって無精卵だったはず。
おなかが痛い。いつもとは何か違う。まるであれをしているときのような、内臓の奥に何かが突っ込まれているような違和感。
あんなことがあったから、精神的なショックで身体もおかしくなっているのかしら。でも。でも……
スーパーで買った卵は、無精卵だった。シシャモの卵も、無精卵だった。
無精卵。孵るはずのないもの。子供が生まれてくるはずのないもの。
それは、まだ他にもある。
「い、いやだ」
下腹部の違和感が、どんどん大きくなっていく。ぎちぎちと、内臓が悲鳴を上げている。
「ねえ、やめてよ」
「おい、どうした。大丈夫か?」
洋輔の声が、かすかに聞こえる。まだふたりだけの生活を楽しみたいからといって、セックスのときは必ずコンドームを着けている洋輔の声が。
「いやだ、ねえ、やめて、出てこないで」
「明日美、ここを開けろよ。どうしたんだよ」
私のおなかの中には、無精卵がある。子宮の中で赤ちゃんになるのを待っていた、だけど、今にも捨てられようとしている、小さな卵子が。
私のおなかが、膨れていく。その中で、何かがもぞもぞと動いている。ぼたぼたと、ナプキンなんかでは吸収しきれないほどに大量の血が、太ももに伝い落ちる。座っていられなくなって、トイレの床に倒れこむ。便器の中に落ちた血が、濁った渦を巻いている。ピシッと音を立てて、急激な膨張に耐え切れなかった下腹部の皮膚が切れる。破水したのか、ピンク色の液体がトイレの床に広がる。あるはずのない胎盤に小さな爪が立てられて、ぐちゃぐちゃと剥がされているのがわかる。ブチッとくぐもった音がして、臍帯が引きちぎられる。ああ、外に出ようともがいている。痛みが子宮から膣へと徐々に移る。痛い痛いイタイッ!
「いやああああああ!!」
私の両足は限界を超えて開き、股関節がゴキリと外れる。そして、鮮やかな色の血にまみれ、羊水でぶよぶよとふやけた小さな手が私の中から――
薄れ行く意識の中、最後に私が聞いたのは、洋輔がトイレのドアを叩く音でも、私の絶叫でもなく、勝ち誇ったような産声だった。
(fin)
